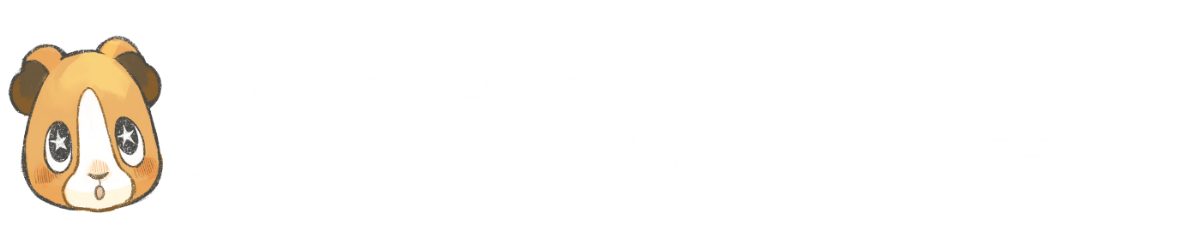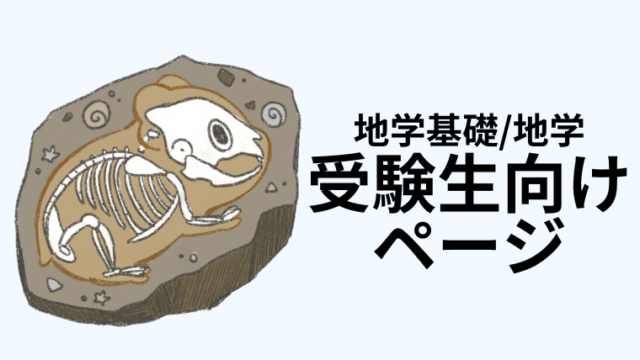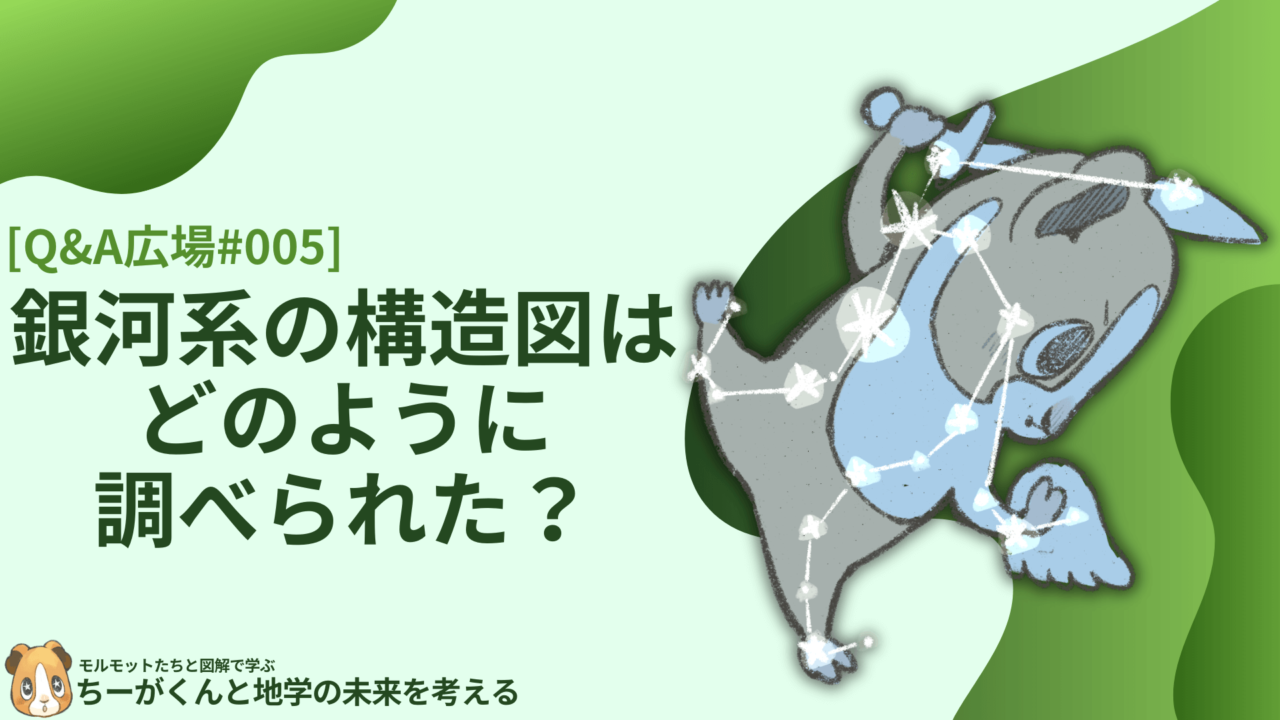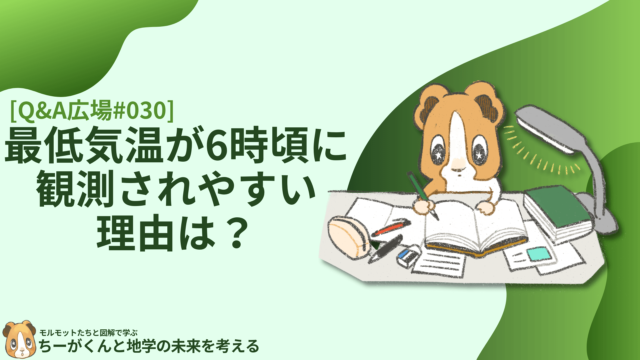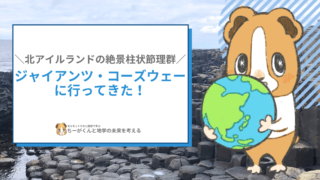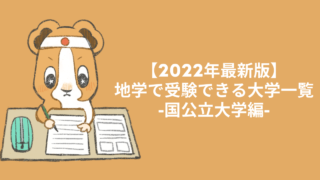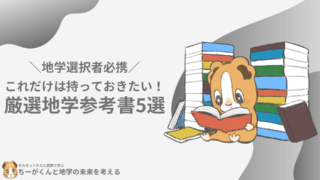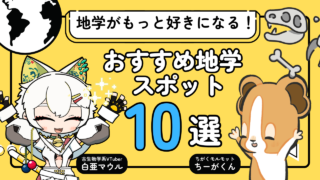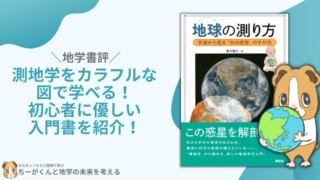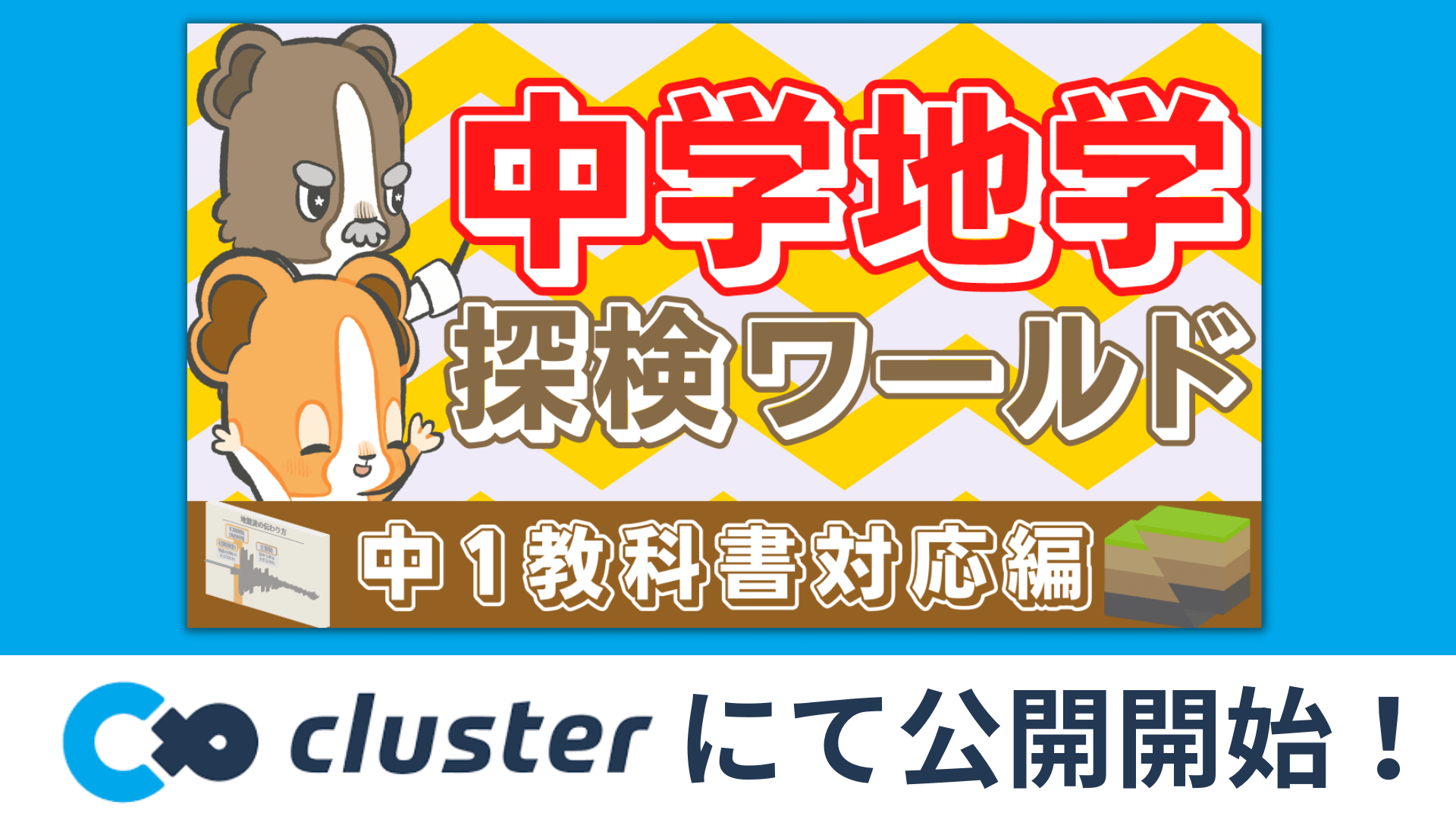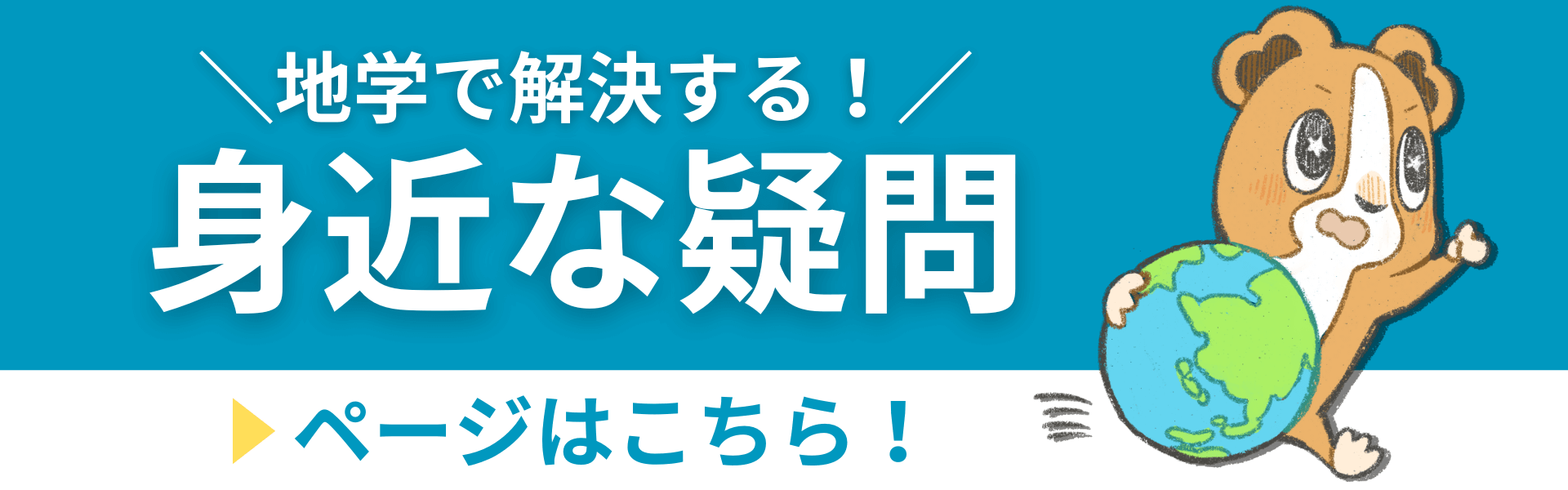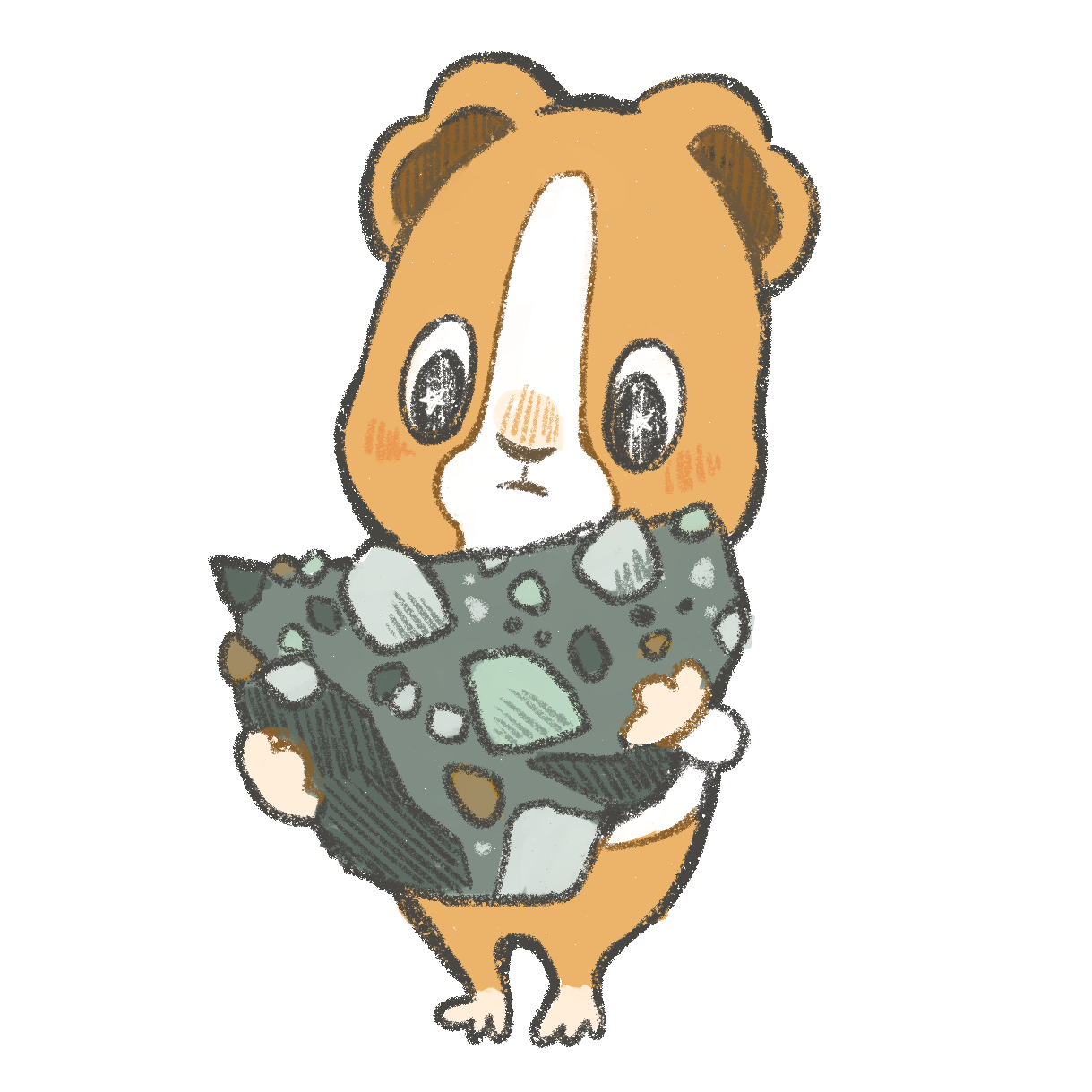スポンサーリンク
ちーがくん
はかせ!今日はこんな質問をいただきました!
質問内容
質問No.5 質問者:高校生 ぶらっくまん
教科書に載っているハローやバルジなどの銀河系の構造図は、どのようにして調べられたのですか?
ちーがくん
確かに、銀河系を横から見てぱしゃっと写真を撮るわけにもいかなそうですし、どうやって調べたのかすごく気になりますよね。
はかせ
いい質問じゃ!銀河系の構造図は、さまざまな観測技術を駆使し、その観測結果を元に想像図として作られておるんじゃよ。
これまでどのような観測が行われてきたか、ざっと紹介していくぞ。
これまでどのような観測が行われてきたか、ざっと紹介していくぞ。
スポンサーリンク
可視光望遠鏡と初期の観測
はかせ
18世紀には、ウィリアム・ハーシェルが巨大な望遠鏡を使って星の数を数え、観測を行ったんじゃ。
ちーがくん
巨大な望遠鏡を使って星の数を1つずつ数えていったんですか!
気の遠くなるような作業ですね!
気の遠くなるような作業ですね!
はかせ
この方法により、銀河系が多数の星で構成される円盤状の構造を持つことが示唆されたんじゃよ。
ハーシェルは銀河系の地図を作成し、その形状を初めて明確にしたんじゃ。
ハーシェルは銀河系の地図を作成し、その形状を初めて明確にしたんじゃ。
ちーがくん
18世紀にもう銀河系の形が分かり始めていたなんて、すごいですね!
セファイド変光星の利用
はかせ
20世紀初頭には、ヘンリエッタ・スワン・リービットという人がセファイド変光星の周期と明るさの関係(周期-光度関係)を発見したんじゃ。
この関係を利用して、ハーロー・シャプレーは銀河系の中心位置を特定し、その大きさを正確に測定したんじゃよ。
この関係を利用して、ハーロー・シャプレーは銀河系の中心位置を特定し、その大きさを正確に測定したんじゃよ。
ちーがくん
変光星って、見かけの明るさが時間によって変化していく星のことですよね?
その時間と明るさに周期性を見つけたんですね!
その時間と明るさに周期性を見つけたんですね!
はかせ
これにより、銀河系が従来考えられていたよりもはるかに大きいことが明らかになったんじゃ。
ちーがくん
セファイド変光星を使ったおかげで銀河系の本当の大きさが分かったんだ!
赤外線望遠鏡
はかせ
次に、赤外線を使った観測が行われたんじゃ。赤外線は星間にある塵(星間塵)による光の吸収を受けにくいため、赤外線望遠鏡を使用することで銀河系の中心部や塵に隠れた部分を観測できるんじゃ。
ちーがくん
赤外線望遠鏡で見えなかった部分が見えるようになったんですね!
はかせ
2003年8月に打ち上げられた赤外線宇宙望遠鏡であるNASAのスピッツァー宇宙望遠鏡は、銀河系の螺旋構造を詳細に観測し、主要な2本の腕が存在することを明らかにしたんじゃ。
これにより、中心部のバルジやディスクの構造がより詳しく理解されたんじゃよ。
これにより、中心部のバルジやディスクの構造がより詳しく理解されたんじゃよ。
ちーがくん
バルジやディスクの構造は赤外線を使った宇宙望遠鏡の観測で理解されたのですね!
電波望遠鏡
はかせ
電波望遠鏡はあまり聞き馴染みが無いかもしれないが、特に水素原子からの放射(21cm線)を利用して、銀河系の構造をさらに詳しく調べるために使用されておる。これは星間ガスの分布を示す重要な手がかりとなるんじゃ。
ちーがくん
電波望遠鏡を使うことで星間ガスの分布まで分かってしまうんですね!
はかせ
この方法で、銀河系の螺旋腕や中央の棒状構造(バルジ)の詳細が明らかになったんじゃよ。
特に、電波観測は塵に隠れた領域も観測できるため、銀河全体の構造を把握するのに役立っておるんじゃ。
特に、電波観測は塵に隠れた領域も観測できるため、銀河全体の構造を把握するのに役立っておるんじゃ。
ちーがくん
そういう風に銀河全体の構造が分かったんですね!
電波望遠鏡で塵に隠れた部分まで観測できるなんて、驚きです!
電波望遠鏡で塵に隠れた部分まで観測できるなんて、驚きです!
まとめ
はかせ
今回は、銀河系の構造図がどのようにして調べられたのかについて学んだぞ。
可視光望遠鏡、赤外線望遠鏡、電波望遠鏡などのさまざまな観測技術を駆使して得られたデータをもとに、銀河系の複雑な構造が詳細に解明されてきたんじゃ。これらの観測により、私たちの銀河の全体像が明らかになっておるんじゃよ。
可視光望遠鏡、赤外線望遠鏡、電波望遠鏡などのさまざまな観測技術を駆使して得られたデータをもとに、銀河系の複雑な構造が詳細に解明されてきたんじゃ。これらの観測により、私たちの銀河の全体像が明らかになっておるんじゃよ。
ちーがくん
銀河系の構造がこんなにも多くの観測技術で明らかにされているなんて、本当に驚きました!
教科書に乗っている図は、こういった観測が積み重なった集大成だということを改めて感じました!
はかせ!今日もありがとうございました!
教科書に乗っている図は、こういった観測が積み重なった集大成だということを改めて感じました!
はかせ!今日もありがとうございました!
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
スポンサーリンク